ちあきなおみ
出勤前のひととき、NHKFMのちあきなおみの特集を聴いています。村松友視のしゃべくりは私にはどうでもいいのですが、この歌手はむかしから好きです。
事実上の引退からずいぶん経ってしまって、もうたぶん彼女の声を聴く機会はないでしょう。それでもYouTubeなどで聴けるのはありがたいです。
唄の好き嫌いに理屈をつけても仕方がないのですが、ちあきの唄を聴いていると、やがて消えていく自分の寂しさをなぐさめてくれるような気がするのです。
だから仕事の前の、しかも朝に聴く唄ではないと思うのですが、本放送を聞き逃してしまったのでいま再放送を聴いているというわけです。
歌謡曲にしろ映画にしろ、いわゆる大衆芸能といわれるのが私たちの人生に強烈な思い出としていつまでも残っているというのは、店を訪れる高齢のお客さんの思い出話からもいつも感じていることですが、そういうことを語らせたら右に出るものはいないという小沢昭一さんが亡くなって、昭和の大衆芸能の語り手がもういなくなってしまったという寂しさは感じます。
いまは録音したり録画したりということができますので、そのまま消えてしまうということはないのですが、それでも臨場感は味わえません。
時として私どもの店は、古本にしろレコードにしろビデオにしろ、そんなはかない思い出をおさめた場所なのかとも思います。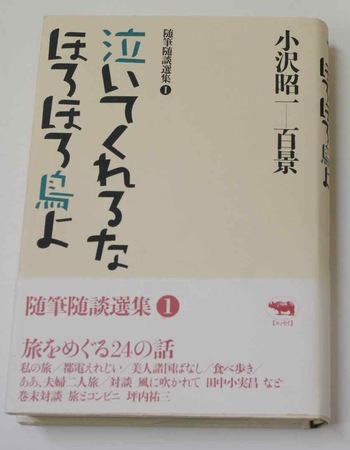
事実上の引退からずいぶん経ってしまって、もうたぶん彼女の声を聴く機会はないでしょう。それでもYouTubeなどで聴けるのはありがたいです。
唄の好き嫌いに理屈をつけても仕方がないのですが、ちあきの唄を聴いていると、やがて消えていく自分の寂しさをなぐさめてくれるような気がするのです。
だから仕事の前の、しかも朝に聴く唄ではないと思うのですが、本放送を聞き逃してしまったのでいま再放送を聴いているというわけです。
歌謡曲にしろ映画にしろ、いわゆる大衆芸能といわれるのが私たちの人生に強烈な思い出としていつまでも残っているというのは、店を訪れる高齢のお客さんの思い出話からもいつも感じていることですが、そういうことを語らせたら右に出るものはいないという小沢昭一さんが亡くなって、昭和の大衆芸能の語り手がもういなくなってしまったという寂しさは感じます。
いまは録音したり録画したりということができますので、そのまま消えてしまうということはないのですが、それでも臨場感は味わえません。
時として私どもの店は、古本にしろレコードにしろビデオにしろ、そんなはかない思い出をおさめた場所なのかとも思います。
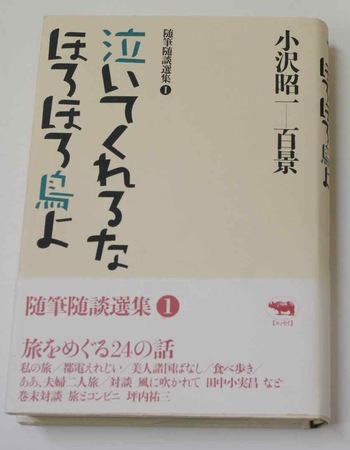
Posted by
南宜堂
at
09:11
│Comments(
0
)
くらもと古本市
少し先の話ですが、諏訪市の宮坂酒造のギャラリー「セラ真澄」で「くらもと古本市」が開催されます。光風舎も参加する予定で準備をすすめています。店売りがふるわない時代です。なんとか直に本をかっていただく機会を作っていきたいと思います。この催しには長野の古本屋さんも何店か出店する予定とか。楽しみです。
同じ2月に長野市でも同様の催しを企画しています。正式に決まったらお知らせします。
名称 くらもと古本市「酒蔵で本を読む」
主催 株式会社バリューブックス http://www.valuebooks.jp/
協力 宮坂醸蔵
会期 2013年02月02日(土)~10日(日)仮
会場 セラ真澄 http://www.cellam
同じ2月に長野市でも同様の催しを企画しています。正式に決まったらお知らせします。
名称 くらもと古本市「酒蔵で本を読む」
主催 株式会社バリューブックス http://www.valuebooks.jp/
協力 宮坂醸蔵
会期 2013年02月02日(土)~10日(日)仮
会場 セラ真澄 http://www.cellam

Posted by
南宜堂
at
08:09
│Comments(
0
)
新年最初の客
3日の日、店のシャッターを半分開けて仕事をしていたら、まだ高校生くらいの少年が入ってきて熱心に本を見はじめました。今日は休みだけれどと告げて、それでも良かったら見ていってくださいと照明を明るくしてあげました。どうも初詣の帰りのようです。ミステリー中心ですが何冊か買ってくれました。
新春から出版をめぐっては厳しいニュースしか聞きません。おそらく世の中の景気が良くなっても本が売れない状況は続くと思われます。そんな中、新年最初のお客さんが高校生とはありがたいことです。
4日から店がはじまりました。取り立てて急にお客さんが増えたということはありません。相変わらずの店内です。今月いっぱいは店内2割引ということにしました。在庫が増えてきたのと、少し本の入れ替えをしたいということと、いちばん売れない時期を乗り切りたいと、いろいろな思惑があってはじめました。ご来店をお待ちしております。
新春から出版をめぐっては厳しいニュースしか聞きません。おそらく世の中の景気が良くなっても本が売れない状況は続くと思われます。そんな中、新年最初のお客さんが高校生とはありがたいことです。
4日から店がはじまりました。取り立てて急にお客さんが増えたということはありません。相変わらずの店内です。今月いっぱいは店内2割引ということにしました。在庫が増えてきたのと、少し本の入れ替えをしたいということと、いちばん売れない時期を乗り切りたいと、いろいろな思惑があってはじめました。ご来店をお待ちしております。

Posted by
南宜堂
at
09:50
│Comments(
0
)
謹賀新年
謹んで新しい年のお慶びを申し上げます。
不思議なもので、5年ほど前からはじめた趣味の歴史が昨年は趣味から仕事になり本を上梓させていただきました。
また、同じく趣味であった古本屋めぐりが昂じて古本屋を営んでおります。
反対に20代からずっと仕事にしていた出版業はいまや開店休業の状態です。ほとんど計画性のない人生の見本のようなものですが、本人はこの着地にけっこう満足しております。
さて、光風舎は新年4日からの営業です。相変わりませず宜しくお願い申し上げます。
不思議なもので、5年ほど前からはじめた趣味の歴史が昨年は趣味から仕事になり本を上梓させていただきました。
また、同じく趣味であった古本屋めぐりが昂じて古本屋を営んでおります。
反対に20代からずっと仕事にしていた出版業はいまや開店休業の状態です。ほとんど計画性のない人生の見本のようなものですが、本人はこの着地にけっこう満足しております。
さて、光風舎は新年4日からの営業です。相変わりませず宜しくお願い申し上げます。

Posted by
南宜堂
at
13:21
│Comments(
0
)
最後の週です。
今年最後の週、寒い毎日です。相変わらず光風舎はお客さんには恵まれませんが、毎日さまざまな方が所用があって来てくれます。昨日は出帳でつん堂さんが、そして「松代藩」の本を売っていただいているWさんも、そして演芸や映画に造詣の深いOさんからたくさんのいい本を買い取らせていただきました。今日もレコードの買い取りが100枚ほどあり、ここのところ本やレコードの買い取りが続いています。
いい本がたくさん集まってきてはいるのですが、残念ながら買うお客さんが少ないので、ネットにまわさざるを得ません。こういうジレンマはあります。
昨日もつん堂さんに、ネットの登録や発送に追われて、ほかの仕事がなかなかできないとこぼしましたら、今の世の中のシステムは誰も幸せにしないようになってますねと言われる。インターネットが普及して私たちの生活はずいぶんと便利になったはずなのに、いつのまにかそれに振り回されるような生活になっている。これはもう後戻りできないのだというのです。
確かにインターネットがなければ、アマゾンがなければ、町の書店も古本屋は居眠りしながら店番をしてても何とかその日暮らしはできたのです。それが今はネットネットで忙しがっているのです。
一方で、インターネットで本を売るという環境がなければ、ウチのような店は多分5年位前に潰れていたなとも思います。ネット販売は生命維持装置のようなもので、外してしまえば生きていくことができないようになってしまっています。
前にこの欄で書いたNさんという80歳を過ぎたお客さんのことですが、時々たくさんの新聞の書評の切り抜きを持って見えます。その中から何冊かを選んで、私がネットに注文して取り寄せて差し上げているのですが、以前はおそらく書店をまわって探して歩いたのだと思います。こういう環境に慣れてしまえば、おそらく一冊の本を求めて書店を訪ね歩くということが徒労にに思えてくるのではないでしょうか。古本屋になかなかお客が来ないわけです。
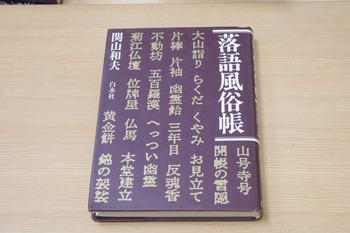
いい本がたくさん集まってきてはいるのですが、残念ながら買うお客さんが少ないので、ネットにまわさざるを得ません。こういうジレンマはあります。
昨日もつん堂さんに、ネットの登録や発送に追われて、ほかの仕事がなかなかできないとこぼしましたら、今の世の中のシステムは誰も幸せにしないようになってますねと言われる。インターネットが普及して私たちの生活はずいぶんと便利になったはずなのに、いつのまにかそれに振り回されるような生活になっている。これはもう後戻りできないのだというのです。
確かにインターネットがなければ、アマゾンがなければ、町の書店も古本屋は居眠りしながら店番をしてても何とかその日暮らしはできたのです。それが今はネットネットで忙しがっているのです。
一方で、インターネットで本を売るという環境がなければ、ウチのような店は多分5年位前に潰れていたなとも思います。ネット販売は生命維持装置のようなもので、外してしまえば生きていくことができないようになってしまっています。
前にこの欄で書いたNさんという80歳を過ぎたお客さんのことですが、時々たくさんの新聞の書評の切り抜きを持って見えます。その中から何冊かを選んで、私がネットに注文して取り寄せて差し上げているのですが、以前はおそらく書店をまわって探して歩いたのだと思います。こういう環境に慣れてしまえば、おそらく一冊の本を求めて書店を訪ね歩くということが徒労にに思えてくるのではないでしょうか。古本屋になかなかお客が来ないわけです。
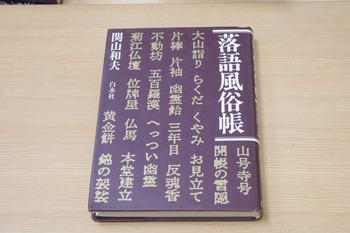
Posted by
南宜堂
at
08:40
│Comments(
0
)
クリスマスキャロル
お客さんのMさんがちくま文庫から出ている駄菓子屋の本を手に、駄菓子の思い出を語って行かれました。先日東京の深川江戸資料館近くのお土産屋さんでニッキアメと金平糖を買ってきました。私には駄菓子屋の味というとなぜかニッキアメなのです。思い出があるのかもしれませんが、思いだせません。
さて、今晩松代テレビというところで「松代藩」の本の紹介をさせてもらうことになりました。Ustreamで配信するテレビのようで、見る人はあまりいないようです。スタッフ全員がボランティアだそうで、出演者ももちろんボランティアです。パーソナリティをつとめるみやもんたさんは愉快な方で、その容貌はご本家によく似ています。
さらに、会津の友より「シュトーレン」という手作りのお菓子をいただきました。少し食べてしまいましたが、今晩はこれを食べてクリスマス気分にと思っています。そういえば小学校の学芸会で「クリスマスキャロル」をやったことがありました。因業な金貸しスクルージの役でした。しばし悪業を悔いたいと思います。
さて、今晩松代テレビというところで「松代藩」の本の紹介をさせてもらうことになりました。Ustreamで配信するテレビのようで、見る人はあまりいないようです。スタッフ全員がボランティアだそうで、出演者ももちろんボランティアです。パーソナリティをつとめるみやもんたさんは愉快な方で、その容貌はご本家によく似ています。
さらに、会津の友より「シュトーレン」という手作りのお菓子をいただきました。少し食べてしまいましたが、今晩はこれを食べてクリスマス気分にと思っています。そういえば小学校の学芸会で「クリスマスキャロル」をやったことがありました。因業な金貸しスクルージの役でした。しばし悪業を悔いたいと思います。
Posted by
南宜堂
at
10:22
│Comments(
0
)
有朋自遠方来。不亦楽乎。
年に一度の歴史仲間の史跡めぐりと忘年会に行って来ました。いつの間にかこの時期に集まるのが恒例となっております。年に一度この日にしかお会いしない人も多くいて、実に不思議な仲間です。
いつも案内していただくKさん、今年はもっとも江戸らしい町ということで深川を案内いただきました。初めて来ました。近くに木場があったり、隅田川が流れているこの町は、今も江戸時代も庶民の町であったようです。深川江戸資料館にはそんな人々が暮らした長屋が再現されていました。
上総屋という米屋の店先も再現されていましたが、ここは米問屋から玄米を仕入れて精米して庶民に売っていた店のようで、その日暮らしの長屋の住民は少しずつ米を買っていたのでしょう。
そういえば江戸詰の松代藩士たちを揶揄する言葉として「松代藩の提灯袋米」というのがあるのを思い出しました。困窮していた江戸詰の藩士たちは、俵で米が買えず、夜こっそりと提灯を下げ米を買いに行ったのだそうです。袋に一升、二升とその日に食べる米を入れてもらって買ったのでしょう。
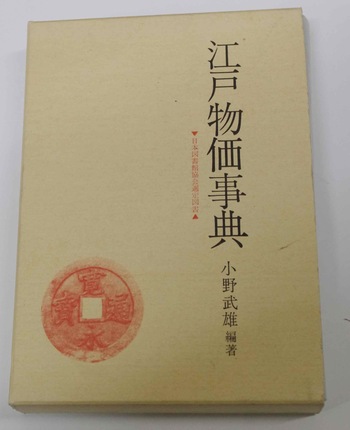
いつも案内していただくKさん、今年はもっとも江戸らしい町ということで深川を案内いただきました。初めて来ました。近くに木場があったり、隅田川が流れているこの町は、今も江戸時代も庶民の町であったようです。深川江戸資料館にはそんな人々が暮らした長屋が再現されていました。
上総屋という米屋の店先も再現されていましたが、ここは米問屋から玄米を仕入れて精米して庶民に売っていた店のようで、その日暮らしの長屋の住民は少しずつ米を買っていたのでしょう。
そういえば江戸詰の松代藩士たちを揶揄する言葉として「松代藩の提灯袋米」というのがあるのを思い出しました。困窮していた江戸詰の藩士たちは、俵で米が買えず、夜こっそりと提灯を下げ米を買いに行ったのだそうです。袋に一升、二升とその日に食べる米を入れてもらって買ったのでしょう。
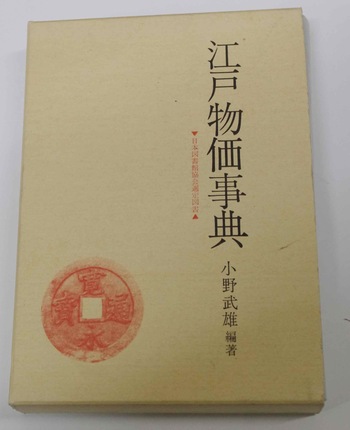
Posted by
南宜堂
at
09:25
│Comments(
0
)
敵はアマゾン
しばらく店のことを書かない日が続きました。冬に入り、相変わらずの低空飛行ですが、店の売上げが悪いのは寒いからだけではなく、本をネットで買う人が増えているからということもあります。そういう傾向がこのところ顕著になっているのではないかと。
そうしたら日経のこんな見出しを今朝発見しました。
コンビニ「敵はアマゾン」 店を飛び出し消費者へ
コンビニが何をやっているかというと、弁当や食品の宅配をはじめたというのです。どうもコンビニの売上げも鈍化しているらしい。そしてその原因としてアマゾンなどのネット通販の影響があるらしいのです。以前町の個人商店でも、近くの店で買わずにネットで買っているというようなことを書きましたが、勝ち組であるコンビニもこんな危機感を持っているようなのです。恐ろしやアマゾンです。何でも呑み込んでしまうようです。
コンビニの狙いはネット環境を持たない高齢者のようで、正面からの対決は避けているようです。さて、我ら零細古本屋はどうやったらアマゾンに対抗できるのか。アマゾンに呑み込まれて、一緒になって通販で売り抜くという方法もありますが、これはもう果てしなき価格競争で消耗が激しいのです。
アマゾンというのは仮想店舗です。例えば「大江健三郎」で検索すると、大江作品の詰まった小部屋に案内してくれて、ここで存分に選んでくださいということになります。時々控えめにこんな本もありますよと声をかけてきますが、原則として勝手に選ばせてくれます。
実店舗の場合は数はすくないけれど、いろいろな本が並んでいて、大江の隣に倉橋由美子の本があったりして、そういう楽しみはあるわけです。
「敵はアマゾン 」などと勇ましいことは言えませんが、アマゾンに浮かんだ筏くらいのことはできるのかもしれません。呑み込まれないで何とか生きるための筏、来年はそんな筏をつくることを考えたいのですが、今は何のアイディアもありません。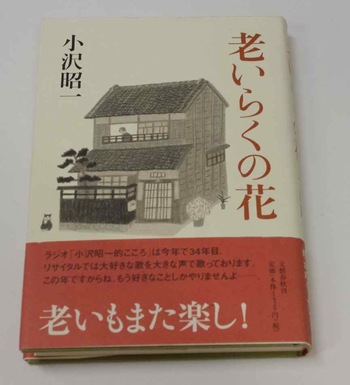
そうしたら日経のこんな見出しを今朝発見しました。
コンビニ「敵はアマゾン」 店を飛び出し消費者へ
コンビニが何をやっているかというと、弁当や食品の宅配をはじめたというのです。どうもコンビニの売上げも鈍化しているらしい。そしてその原因としてアマゾンなどのネット通販の影響があるらしいのです。以前町の個人商店でも、近くの店で買わずにネットで買っているというようなことを書きましたが、勝ち組であるコンビニもこんな危機感を持っているようなのです。恐ろしやアマゾンです。何でも呑み込んでしまうようです。
コンビニの狙いはネット環境を持たない高齢者のようで、正面からの対決は避けているようです。さて、我ら零細古本屋はどうやったらアマゾンに対抗できるのか。アマゾンに呑み込まれて、一緒になって通販で売り抜くという方法もありますが、これはもう果てしなき価格競争で消耗が激しいのです。
アマゾンというのは仮想店舗です。例えば「大江健三郎」で検索すると、大江作品の詰まった小部屋に案内してくれて、ここで存分に選んでくださいということになります。時々控えめにこんな本もありますよと声をかけてきますが、原則として勝手に選ばせてくれます。
実店舗の場合は数はすくないけれど、いろいろな本が並んでいて、大江の隣に倉橋由美子の本があったりして、そういう楽しみはあるわけです。
「敵はアマゾン 」などと勇ましいことは言えませんが、アマゾンに浮かんだ筏くらいのことはできるのかもしれません。呑み込まれないで何とか生きるための筏、来年はそんな筏をつくることを考えたいのですが、今は何のアイディアもありません。
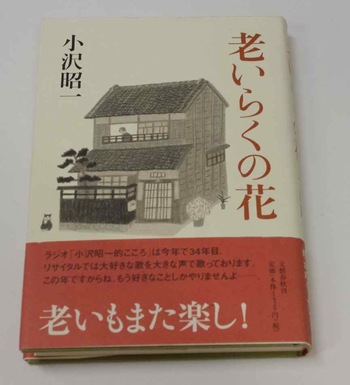
Posted by
南宜堂
at
09:10
│Comments(
0
)
畜生道の地球
普段はあまりツィッターは見ないのですが、選挙の夜はさすが私がフォローしている人たちがどんな発言をするのか興味があったので、タイムラインを追いました。その感想についてはブログにも書いたので繰り返しませんが、皮肉な感想を記させていただきますと、いわゆる物書きの人たちが選挙結果にはほとんど関心を示さないかのように発言していないことです。仕事に影響するわけで、あまり旗幟を鮮明にしない方がいいと考えたのか。私は物書きではありませんが、商売をしている身としてはあまりはっきりしたことは言わない方が賢明なのかもしれないと思った次第です。
と言いながらも、この結果にはやりきれない思いがしています。脱原発や平和よりも景気を選んだということに対してです。もちろん景気はいいにこしたことはありませんが、かといって原発の推進や軍備の強化を目指す人たちに一票をいれることはないじゃないかと思ってしまいます。
もう何十年も前のテレビドラマですが「パンとあこがれ」のことを思い出しました。新宿中村屋を創業した相馬愛藏と黒光夫妻を主人公にしたドラマでした。この二人の息子が反戦運動をして刑務所に入り、出所した彼のもとに召集令状が届きます。この息子が従業員たちを前に別れの挨拶をします。戦争はどんどん激しくなっていくね。自分それに反対していたけれど、結局転向してしまった。これからはもっと大変な世の中になるのだけれど、誰も反対をしなかったのだから仕方がない。そんなような内容だったと思います。太平洋戦争前夜のことです。今はそんな暗黒の時代とは違うのだ。言論の自由があって、誰でも戦争反対を主張できる。その通りだと思います。しかし、反中国、反北朝鮮の過激な発言や株価が上がって本当に嬉しそうな投資家の姿を見ていると、戦争反対をかき消してしまうほどの大きな波がやってくるのかもしれないという恐ろしさを感じます。戦前の社会でも戦争反対を言うものは非国民と思われていたのですから。
相馬黒光は仙台藩士の娘です。来年の大河ドラマは会津藩士の娘である新島八重が主人公なのだそうです。この女性、どんな人だったのかよくは知りません。スペンサー銃を持って官軍相手に戦ったということだけが強調されているようです。明治新政府を作った薩摩や長州に良い感情を持っていない人たちはこのドラマに大きな期待を寄せているようですが
、昭和のはじめ軍国化する政府に異議を唱え続けた東北人のことは知られていないようです。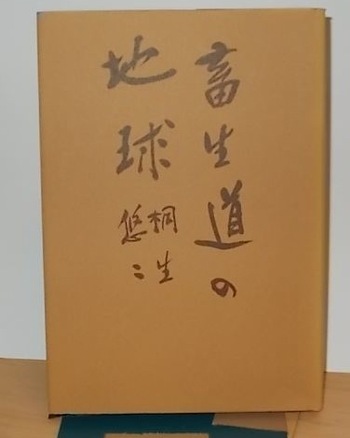
と言いながらも、この結果にはやりきれない思いがしています。脱原発や平和よりも景気を選んだということに対してです。もちろん景気はいいにこしたことはありませんが、かといって原発の推進や軍備の強化を目指す人たちに一票をいれることはないじゃないかと思ってしまいます。
もう何十年も前のテレビドラマですが「パンとあこがれ」のことを思い出しました。新宿中村屋を創業した相馬愛藏と黒光夫妻を主人公にしたドラマでした。この二人の息子が反戦運動をして刑務所に入り、出所した彼のもとに召集令状が届きます。この息子が従業員たちを前に別れの挨拶をします。戦争はどんどん激しくなっていくね。自分それに反対していたけれど、結局転向してしまった。これからはもっと大変な世の中になるのだけれど、誰も反対をしなかったのだから仕方がない。そんなような内容だったと思います。太平洋戦争前夜のことです。今はそんな暗黒の時代とは違うのだ。言論の自由があって、誰でも戦争反対を主張できる。その通りだと思います。しかし、反中国、反北朝鮮の過激な発言や株価が上がって本当に嬉しそうな投資家の姿を見ていると、戦争反対をかき消してしまうほどの大きな波がやってくるのかもしれないという恐ろしさを感じます。戦前の社会でも戦争反対を言うものは非国民と思われていたのですから。
相馬黒光は仙台藩士の娘です。来年の大河ドラマは会津藩士の娘である新島八重が主人公なのだそうです。この女性、どんな人だったのかよくは知りません。スペンサー銃を持って官軍相手に戦ったということだけが強調されているようです。明治新政府を作った薩摩や長州に良い感情を持っていない人たちはこのドラマに大きな期待を寄せているようですが
、昭和のはじめ軍国化する政府に異議を唱え続けた東北人のことは知られていないようです。
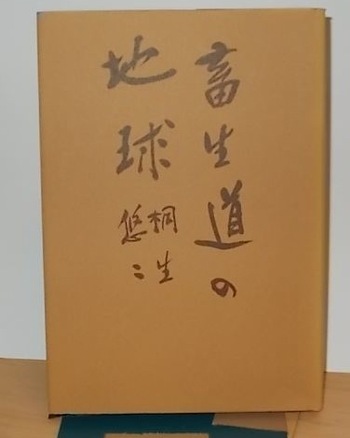
Posted by
南宜堂
at
10:30
│Comments(
0
)
俺たちはジョン・レノンみたいじゃないか。
今回の選挙の最大の争点は「景気回復」なのだそうです。確かに、私のような零細商売も景気の悪さは実感しています。いや、これは低所得者層ほど切実なのでしょう。
で、まあ景気を何とかしてくれということなのでしょうが、原発のこととか憲法のこととかは二の次でいいのでしょうか。
昨日から今日にかけてツイッターやブログで見つけた二人の言葉を紹介します。
「この国の憲法第9条はまるでジョン・レノンの考え方みたいじゃないか?
戦争を放棄して世界の平和のためにがんばるって言っているんだぜ。俺たちはジョン・レノンみたいじゃないか。戦争はやめよう。平和に生きよう。みんな平等に暮らそう。きっと幸せになれるよ。」
「お金はそんなに大切か????
お金があっても幸せとは限らないし、無いからといって不幸ではない。。。
幸せか不幸かは他人が決める事ではなく私が決める事。。。
でも私が出会った台湾女性、ほとんどの人がお金は結婚の絶対条件。。。。
でもさ。。。。それってどうなんだろう???
裕福でなくとも生活できて幸せならそれでいいのはバカなのか・・・・???
お金で人の価値をはかる人間に自分は絶対になりたくない・・・・」
最初のは湯川れい子さんが紹介した忌野清志郎の言葉です。そして、二番目のは私の次女のブログです。彼女が生まれてから我が家は貧乏の連続で、彼女もずいぶんと辛い思いをしたのだと思います。それで日本にいる頃は結婚するならお金持ちと言っていたのですが、いま台湾に暮らしていて別の価値観を持ち始めているようです。
今の日本の状況というのは、どこか戦前の日中戦争前夜の状況に似ているような気がします。景気が悪くて、その捌け口として大陸への侵略がはじまったというような。
尖閣の領空を侵犯する中国はけしからん、北朝鮮のミサイルはけしからん、なんとかしろよという風潮は国民の間に鬱憤が溜まっているからなのでしょう。そんな中拉致被害者の皆さんの会見が報道されていました。時間だけが過ぎていく焦りの中、しかし決して力ずくでは解決しないということは十分わかっておられるようでした。
虚しいながらも、ささやかな意思表示のために投票に行ってきます。
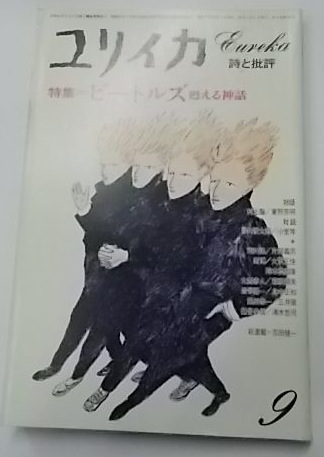
で、まあ景気を何とかしてくれということなのでしょうが、原発のこととか憲法のこととかは二の次でいいのでしょうか。
昨日から今日にかけてツイッターやブログで見つけた二人の言葉を紹介します。
「この国の憲法第9条はまるでジョン・レノンの考え方みたいじゃないか?
戦争を放棄して世界の平和のためにがんばるって言っているんだぜ。俺たちはジョン・レノンみたいじゃないか。戦争はやめよう。平和に生きよう。みんな平等に暮らそう。きっと幸せになれるよ。」
「お金はそんなに大切か????
お金があっても幸せとは限らないし、無いからといって不幸ではない。。。
幸せか不幸かは他人が決める事ではなく私が決める事。。。
でも私が出会った台湾女性、ほとんどの人がお金は結婚の絶対条件。。。。
でもさ。。。。それってどうなんだろう???
裕福でなくとも生活できて幸せならそれでいいのはバカなのか・・・・???
お金で人の価値をはかる人間に自分は絶対になりたくない・・・・」
最初のは湯川れい子さんが紹介した忌野清志郎の言葉です。そして、二番目のは私の次女のブログです。彼女が生まれてから我が家は貧乏の連続で、彼女もずいぶんと辛い思いをしたのだと思います。それで日本にいる頃は結婚するならお金持ちと言っていたのですが、いま台湾に暮らしていて別の価値観を持ち始めているようです。
今の日本の状況というのは、どこか戦前の日中戦争前夜の状況に似ているような気がします。景気が悪くて、その捌け口として大陸への侵略がはじまったというような。
尖閣の領空を侵犯する中国はけしからん、北朝鮮のミサイルはけしからん、なんとかしろよという風潮は国民の間に鬱憤が溜まっているからなのでしょう。そんな中拉致被害者の皆さんの会見が報道されていました。時間だけが過ぎていく焦りの中、しかし決して力ずくでは解決しないということは十分わかっておられるようでした。
虚しいながらも、ささやかな意思表示のために投票に行ってきます。
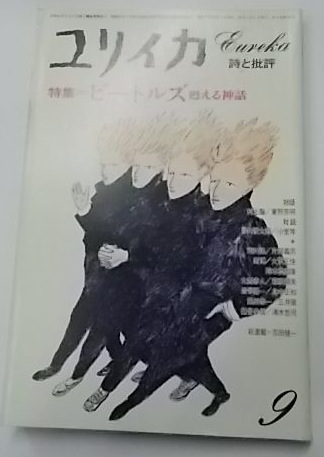
Posted by
南宜堂
at
10:19
│Comments(
0
)
田村騒動記
時は元禄15年12月14日、赤穂浪士討ち入りの日であります。新暦でいうと1月末のようですから、雪が積もっていたというのも頷けます。討ち入りは深夜に行われたそうで、47人が徒党を組んで夜中に押し入るとは穏やかではない。卑怯のような気がします。
現在放映中の時代劇「薄桜記」はこの事件をモチーフにしたもので、どうも主人公丹下典膳は吉良の用心棒となるらしく、親友の堀部安兵衛と戦うことになりそうです。
発端は浅野内匠頭の刃傷なのですが、この原因がよくわからない。吉良のいじめが原因という説が有力で、これなら仇討ちもやむを得ないということなのですが、実際の所は内匠頭が神経を病んでいたという説もありますし、そうであれば吉良上野介はとんだとばっちりです。
いずれにせよ「薄桜記」を見ていますと、討ち入りは当然、討ち入りしなければ収まらないといった風潮ができていたようで、吉良邸もそれに備えています。いつの時代でもそういった流れはあるようで、今度の選挙も民主党は負けて当然、安倍だの石原だの橋下ならなんかやってくれるだろうといった風潮とよく似ているようです。国防軍ができて原発もどんどん稼働する世の中になっていくのでしょう。
話が忠臣蔵からそれてしまいました。この義挙の物語に大野九郎兵衛という仇役がいます。赤穂開城の際、絶対恭順を主張して逐電したという赤穂浪士好きから見たらとんでもない男なのですが、これが少々松代と関係があります。
大野は江戸に逃げて密かに暮らしていたようで、その息子もまた田村半右衛門の名で江戸で浪人をしていました。この半右衛門がどうしたいきさつからか松代藩に雇われ、財政再建を任されたのです。
半右衛門が取った政策というのが、領民には過酷な年貢を課し、藩士には徹底的な倹約を要求したということですから、大反発をくらい、ついには一揆を招いてしまいました。半右衛門は松代にはいられなくなり、坊主に変装して逃げ出したという結果となりました。この顛末を記した「田村騒動記」というのが松代に伝わっていますが、真偽のほどはわかりません。
現在放映中の時代劇「薄桜記」はこの事件をモチーフにしたもので、どうも主人公丹下典膳は吉良の用心棒となるらしく、親友の堀部安兵衛と戦うことになりそうです。
発端は浅野内匠頭の刃傷なのですが、この原因がよくわからない。吉良のいじめが原因という説が有力で、これなら仇討ちもやむを得ないということなのですが、実際の所は内匠頭が神経を病んでいたという説もありますし、そうであれば吉良上野介はとんだとばっちりです。
いずれにせよ「薄桜記」を見ていますと、討ち入りは当然、討ち入りしなければ収まらないといった風潮ができていたようで、吉良邸もそれに備えています。いつの時代でもそういった流れはあるようで、今度の選挙も民主党は負けて当然、安倍だの石原だの橋下ならなんかやってくれるだろうといった風潮とよく似ているようです。国防軍ができて原発もどんどん稼働する世の中になっていくのでしょう。
話が忠臣蔵からそれてしまいました。この義挙の物語に大野九郎兵衛という仇役がいます。赤穂開城の際、絶対恭順を主張して逐電したという赤穂浪士好きから見たらとんでもない男なのですが、これが少々松代と関係があります。
大野は江戸に逃げて密かに暮らしていたようで、その息子もまた田村半右衛門の名で江戸で浪人をしていました。この半右衛門がどうしたいきさつからか松代藩に雇われ、財政再建を任されたのです。
半右衛門が取った政策というのが、領民には過酷な年貢を課し、藩士には徹底的な倹約を要求したということですから、大反発をくらい、ついには一揆を招いてしまいました。半右衛門は松代にはいられなくなり、坊主に変装して逃げ出したという結果となりました。この顛末を記した「田村騒動記」というのが松代に伝わっていますが、真偽のほどはわかりません。

Posted by
南宜堂
at
08:45
│Comments(
0
)
冥土の旅の一里塚
今日は私にとって一年に一度しかない特別な日なのですが、こんな日はしみじみと「人の世は冥土の旅」というフレーズを思い出します。何日か前ポロ氏が今日は津田君の39回目の命日だとフェイスブックで書いていましたが、その日の朝私は京都にいて彼の訃報を知ったのだなと思い出したのでした。
何人かの親しい人たちを送り、三人の新しい命に出会い、ここまでやってきたわけですが、冥土(目的地)が近づいたせいかいろいろ考えるようになったのでしょう。
冥土の旅といえば、数日前小沢昭一が亡くなりました。随分前になりますが、私が当時勤めていた出版社で、永六輔や小沢昭一の芝居の長野公演をプロデュースしたことがあって、今は無き長野市民会館のロビーで切符もぎりをしたことがありました。
昨日たまたま小沢昭一の本を見ていたら、浪花節に触れた部分がありました。私などはリアルタイムでは聞いていなかったのですが、二代目広沢虎造の声を褒めちぎっていました。吉川潮の小説を読むと、随分と破天荒な行き方をした人のようですが、芸は素晴らしかったようです。
小沢さんはその本の中で、清水のあたりを通ると「旅ゆけば駿河の国に茶の香り」という虎造節が思わず口に出ると書いていましたが、さしずめ今朝の心境は「旅ゆけば冥土の旅の一里塚、目出度くもあり目出度くもなし」というところでしょうか。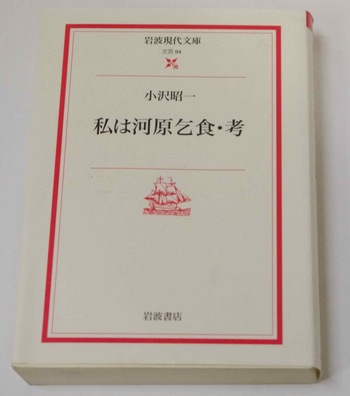
何人かの親しい人たちを送り、三人の新しい命に出会い、ここまでやってきたわけですが、冥土(目的地)が近づいたせいかいろいろ考えるようになったのでしょう。
冥土の旅といえば、数日前小沢昭一が亡くなりました。随分前になりますが、私が当時勤めていた出版社で、永六輔や小沢昭一の芝居の長野公演をプロデュースしたことがあって、今は無き長野市民会館のロビーで切符もぎりをしたことがありました。
昨日たまたま小沢昭一の本を見ていたら、浪花節に触れた部分がありました。私などはリアルタイムでは聞いていなかったのですが、二代目広沢虎造の声を褒めちぎっていました。吉川潮の小説を読むと、随分と破天荒な行き方をした人のようですが、芸は素晴らしかったようです。
小沢さんはその本の中で、清水のあたりを通ると「旅ゆけば駿河の国に茶の香り」という虎造節が思わず口に出ると書いていましたが、さしずめ今朝の心境は「旅ゆけば冥土の旅の一里塚、目出度くもあり目出度くもなし」というところでしょうか。
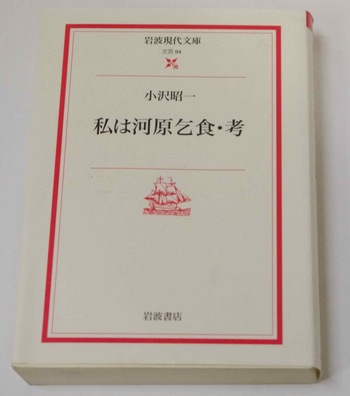
Posted by
南宜堂
at
10:01
│Comments(
0
)
雪の日に思うこと
長野も本格的な雪となりました。まだ冬タイヤに履き替えていなかったので、電車とバスを利用して店まで来ました。そういう人が多いのか、車内はけっこう混み合っていました。
最近は公共交通機関を利用することが多いのですが、自分でハンドルを握らなくていいというのは快適です。外の景色などもよく見えますし、思わぬ発見もあります。しかし、郊外に用事があったり買い物があったりすると、どうしても車がないと用が足せません。それにバス代は高い。
町から郊外に人を奪ったのは車です。私の店のある東町周辺はかつては長野の中心で、近郷近在の人たちが商売や買い物に訪れて栄えた町です。それが今は見る影もないほどに衰退してしまいました。
私の子どもの頃は、西後町の税務署のあるあたり(長野以外の方は何を言っているのか不明と思います。申し訳ありません。)に川中島バスの発着所があって、いつも人で混雑していました。その近くの大門町というバス停で私は乗るのですが、今日のような雪の日でさえ、乗る人は私のほかに一人か二人です。今人の動きは郊外に向かっていて、このあたりは訪れる人も住む人もめっきり少なくなっています。
こんな雪の日に思うのは、できれば雪の降った日は車の運転をしなくてもいいような生活をしたい。老後(今も老後ですが)は車無しでも生活できるようにしたいということです。そのひとつの方法として店のあたりに住む、または店の奥で暮らすということがあります。現在の店はそういう構造になっていないので無理ですが、できればそんな店をみつけたいと思っています。病院も飲み屋(私は下戸ですからこれはかんけいありませんが)も善光寺も歩いて行ける距離にあるわけで、これは理想です。
そのためにも店でもう少し売れてほしいと思っているのですが、なかなかそうはなりません。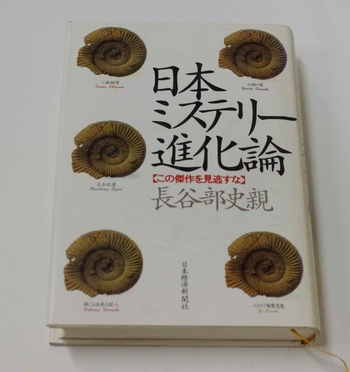
最近は公共交通機関を利用することが多いのですが、自分でハンドルを握らなくていいというのは快適です。外の景色などもよく見えますし、思わぬ発見もあります。しかし、郊外に用事があったり買い物があったりすると、どうしても車がないと用が足せません。それにバス代は高い。
町から郊外に人を奪ったのは車です。私の店のある東町周辺はかつては長野の中心で、近郷近在の人たちが商売や買い物に訪れて栄えた町です。それが今は見る影もないほどに衰退してしまいました。
私の子どもの頃は、西後町の税務署のあるあたり(長野以外の方は何を言っているのか不明と思います。申し訳ありません。)に川中島バスの発着所があって、いつも人で混雑していました。その近くの大門町というバス停で私は乗るのですが、今日のような雪の日でさえ、乗る人は私のほかに一人か二人です。今人の動きは郊外に向かっていて、このあたりは訪れる人も住む人もめっきり少なくなっています。
こんな雪の日に思うのは、できれば雪の降った日は車の運転をしなくてもいいような生活をしたい。老後(今も老後ですが)は車無しでも生活できるようにしたいということです。そのひとつの方法として店のあたりに住む、または店の奥で暮らすということがあります。現在の店はそういう構造になっていないので無理ですが、できればそんな店をみつけたいと思っています。病院も飲み屋(私は下戸ですからこれはかんけいありませんが)も善光寺も歩いて行ける距離にあるわけで、これは理想です。
そのためにも店でもう少し売れてほしいと思っているのですが、なかなかそうはなりません。
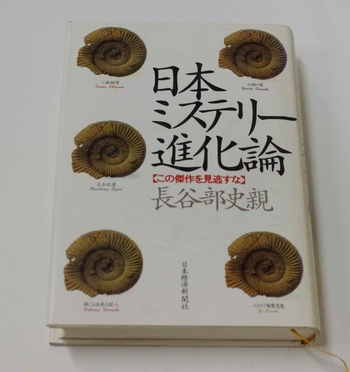
Posted by
南宜堂
at
00:09
│Comments(
0
)
民主主義
昨日の地震はまったく気がつかず、インターネットの速報で知りました。東北には知り合いが多く心配でしたが、大きな被害がなくて幸いでした。これだけ地震の多い国で原発を推進しようという人たちは何を考えているのか。そういう政党が今度の選挙では圧勝する予想ですが、これが世論の現実なのでしょうか。
原発もそうですが、国防も教育でも何か正義とか大きな声で言っている人たちがこの国を指導していくことになりそうな情勢です。
民主主義とは大多数の意見が入れにれる社会であるということですから、私なんかは少数意見で、そういう少数意見は入れられないということなのでしょうか。
確か宮本常一の本にある島に調査に行ったときのことが書かれていて、そこでは住民皆が納得するまで何回でも集会がもたれるのだということがありました。
原発をどんどん動かし、国防軍を強め、いじめは正義の力でなくす、そういう社会は私には居心地が悪い社会です。むなしくともそうならないように一票は行使するつもりです。
原発もそうですが、国防も教育でも何か正義とか大きな声で言っている人たちがこの国を指導していくことになりそうな情勢です。
民主主義とは大多数の意見が入れにれる社会であるということですから、私なんかは少数意見で、そういう少数意見は入れられないということなのでしょうか。
確か宮本常一の本にある島に調査に行ったときのことが書かれていて、そこでは住民皆が納得するまで何回でも集会がもたれるのだということがありました。
原発をどんどん動かし、国防軍を強め、いじめは正義の力でなくす、そういう社会は私には居心地が悪い社会です。むなしくともそうならないように一票は行使するつもりです。

Posted by
南宜堂
at
09:09
│Comments(
0
)
松代のボランティア
冷たい雨の降る中を松代まで行って来ました。真田宝物館は休館日で町の中に観光客は見えません。
町づくりセンターというのが町の中心部にあって、ここが町おこしボランティアの方々の拠点になっているようです。さらには町内あちらこちらに一般に公開されている武家屋敷などがあり、ここの管理運営にもボランティアの人たちが多く関わっており、松代の観光はこういったボランティアの人たちに支えられているという印象を受けました。
お会いしたのは松代テレビの「みやもんた」さん、もちろん本名ではありません。松代テレビはUstreamを使ったインターネットのテレビで、古本業界でいえば「わめぞテレビ」や「しのばずブックストリーム」のようなものです。
今月の24日にこのテレビに出演することになり、その打ち合わせに出かけたのです。本を売るために恥をかくようなものですが、ほとんど視聴者がいないということでちょっと安心して引き受けた次第です。数十人単位だそうで、出演者があちこちに吹聴して視聴率を上げているようです。
みやもんた(芸名)もボランティアで、病院を退職して松代の町おこしボランティアでテレビのキャスターをしているのです。雑談のなかから真田信之と小野お通のことを話そうということになりました。この二人については池波正太郎が「真田太平記」で恋愛関係にあったように書いていますが、これはファクションでしょう。お通の方が5歳年上ですし、信之が一方的に憧れていたのではと思います。
「小野お通は、永禄十年(一五六八)に美濃の国で、織田信長に仕える小野正秀の娘として生まれた。浅井茶々、後の淀殿に仕えたといわれるが、その経歴はよくわかっていない。人形浄瑠璃のもとともなったといわれる「浄瑠璃姫 十二段物語」はお通の作とされ、豊臣秀吉の側室淀殿が秀頼身ごもった時に慰みにと献上されたものであるという。詩歌や琴、書画などに秀でた才能をもった女性で、その点が信之が強く惹かれた理由であったろう。」(「シリーズ藩物語 松代藩」より)
町づくりセンターというのが町の中心部にあって、ここが町おこしボランティアの方々の拠点になっているようです。さらには町内あちらこちらに一般に公開されている武家屋敷などがあり、ここの管理運営にもボランティアの人たちが多く関わっており、松代の観光はこういったボランティアの人たちに支えられているという印象を受けました。
お会いしたのは松代テレビの「みやもんた」さん、もちろん本名ではありません。松代テレビはUstreamを使ったインターネットのテレビで、古本業界でいえば「わめぞテレビ」や「しのばずブックストリーム」のようなものです。
今月の24日にこのテレビに出演することになり、その打ち合わせに出かけたのです。本を売るために恥をかくようなものですが、ほとんど視聴者がいないということでちょっと安心して引き受けた次第です。数十人単位だそうで、出演者があちこちに吹聴して視聴率を上げているようです。
みやもんた(芸名)もボランティアで、病院を退職して松代の町おこしボランティアでテレビのキャスターをしているのです。雑談のなかから真田信之と小野お通のことを話そうということになりました。この二人については池波正太郎が「真田太平記」で恋愛関係にあったように書いていますが、これはファクションでしょう。お通の方が5歳年上ですし、信之が一方的に憧れていたのではと思います。
「小野お通は、永禄十年(一五六八)に美濃の国で、織田信長に仕える小野正秀の娘として生まれた。浅井茶々、後の淀殿に仕えたといわれるが、その経歴はよくわかっていない。人形浄瑠璃のもとともなったといわれる「浄瑠璃姫 十二段物語」はお通の作とされ、豊臣秀吉の側室淀殿が秀頼身ごもった時に慰みにと献上されたものであるという。詩歌や琴、書画などに秀でた才能をもった女性で、その点が信之が強く惹かれた理由であったろう。」(「シリーズ藩物語 松代藩」より)

Posted by
南宜堂
at
09:18
│Comments(
0
)
師走
12月最初の週末です。気温が下がり雪も舞いました。こんな日はほんとうに閑です。雨が降ればてきめんに売上げは落ちる、晴れたからといって売れる保証はない。某古書店主の言葉ですが、けだし名言です。
11月は店売り1に対しネット2の割合となり、店売りの前途は多難です。ネットでそこそこ売れているから何とかやっているという状態が続いています。ネットで売れているのだから品揃えが悪いわけではないと思うのですが、共同経営者に言わせると、お客が来ないのだから売れるはずがない。これまた名言です。
きょう本を売りに見えたMさんが小一時間ばかり話をして行かれましたが、この間来店客はゼロで「ほんとうに客が来ないね」と感心していかれました。
まだ私が古本屋をやる前、休日は車を県庁の駐車場に置いて(土日は無料開放されています)、ふくやか万両でラーメンを食べ、善光寺周辺の小路をぶらぶら歩き、古本屋を覗き、大門町のえんがわで珈琲を飲んで帰る、そんな過ごし方をしていました。まだネットで本を買う習慣はなく、別に目当ての本がなくとも、1冊か2冊買ったものです。
あれは古き良き時代の白昼夢のようなものだったのか。今は帳場のこちら側に座る身となりましたが、妙に懐かしい日々でした。売れなくとも店売りを辞めたくはないのは、そんないい思い出があるからなのかもしれません。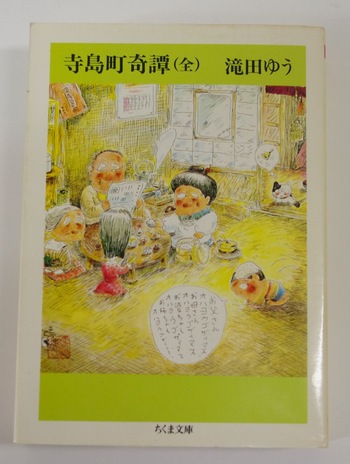
11月は店売り1に対しネット2の割合となり、店売りの前途は多難です。ネットでそこそこ売れているから何とかやっているという状態が続いています。ネットで売れているのだから品揃えが悪いわけではないと思うのですが、共同経営者に言わせると、お客が来ないのだから売れるはずがない。これまた名言です。
きょう本を売りに見えたMさんが小一時間ばかり話をして行かれましたが、この間来店客はゼロで「ほんとうに客が来ないね」と感心していかれました。
まだ私が古本屋をやる前、休日は車を県庁の駐車場に置いて(土日は無料開放されています)、ふくやか万両でラーメンを食べ、善光寺周辺の小路をぶらぶら歩き、古本屋を覗き、大門町のえんがわで珈琲を飲んで帰る、そんな過ごし方をしていました。まだネットで本を買う習慣はなく、別に目当ての本がなくとも、1冊か2冊買ったものです。
あれは古き良き時代の白昼夢のようなものだったのか。今は帳場のこちら側に座る身となりましたが、妙に懐かしい日々でした。売れなくとも店売りを辞めたくはないのは、そんないい思い出があるからなのかもしれません。
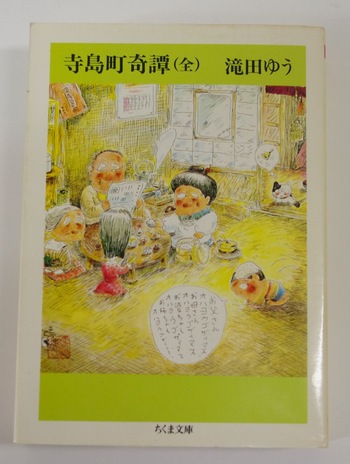
Posted by
南宜堂
at
01:33
│Comments(
0
)
猫の忠信
ラジオで「猫の忠信」という関西落語をやっておりましたが、ここに「難波戦記・真田の抜け穴」という講釈を聞きに行ったというようなことがありました。「難波戦記」というのは大坂の陣を題材にしたもので、「真田三代記」の元になった話だということであります。どちらかというと徳川方に贔屓したものなのだそうですが、それにしても大坂の陣を題材にした講釈が演じられていたということです。
この落語「猫の忠信」の下敷きとなっている話は歌舞伎や浄瑠璃で有名な「義経千本桜」なのですが、これまた江戸時代には庶民の娯楽としてもてはやされたようです。能、歌舞伎、講談、下っては立川文庫まで、大衆にとっての歴史は娯楽とほとんど紙一重のようなものだったのでしょう。
歴史学という学問が確立された現代において、江戸時代のような娯楽としての歴史はなくなってしまったのかというと、それが結構しぶとく生き残っているようです。例えば先日紹介した雑誌の「歴史街道」です。真田特集のキャッチコピーは「家名か武名か漢の意地か 六文銭の旗を掲げ、兄弟それぞれの戦いに挑む」とありました。関ヶ原の戦いから大坂夏の陣までの真田の歴史を、こういう主観的なしかも一方的な言葉でまとめてしまっていいものなのかどうか、私などは大いに疑問に思います。また、幸村が大坂夏の陣で最後の決戦に臨もうとする朝、江戸にいる信之は弟に語りかけます。「いよいよその日が参ったな」と。しかしよく考えれば携帯電話もない時代に、どうして大坂にいる弟の行動を同時進行で知ることができるのでしょうか。「そこは「以心電信」心を電波に乗せて伝えたのよ」などと落語的な解釈をするのが粋なのかもしれません。
軍談家や講釈師や戯作者、現代では小説家などもその仲間に入るのかもしれませんが、こういった人たちが脚色した歴史の方が実証的な歴史よりは数段面白いのも確かです。私たちは司馬遼太郎が脚色した坂本龍馬や土方歳三、池波正太郎が脚色した真田幸村や信之を以て歴史を語っているようなところがあります。
通俗の歴史をフィクションと知って娯楽として愉しむ分には罪がないわけですが、そこに「歴史にまなぶ何々」などと付くと「ちょっと待ってくれよ」ということにもなります。
最近評判の「日本維新の会」なる集団、維新八策なるものを掲げているようですが、坂本龍馬の「船中八策」と紛らわしくて警戒してしまいます。この「維新の会」の二人の親分が明治維新や昭和維新を念頭に世直しを考えているのだとしたら、面白がるだけではなく、実証的に歴史を学んで。維新なるものが何をもたらしたのか、しっかりと見極めなければいかんとも思います。

この落語「猫の忠信」の下敷きとなっている話は歌舞伎や浄瑠璃で有名な「義経千本桜」なのですが、これまた江戸時代には庶民の娯楽としてもてはやされたようです。能、歌舞伎、講談、下っては立川文庫まで、大衆にとっての歴史は娯楽とほとんど紙一重のようなものだったのでしょう。
歴史学という学問が確立された現代において、江戸時代のような娯楽としての歴史はなくなってしまったのかというと、それが結構しぶとく生き残っているようです。例えば先日紹介した雑誌の「歴史街道」です。真田特集のキャッチコピーは「家名か武名か漢の意地か 六文銭の旗を掲げ、兄弟それぞれの戦いに挑む」とありました。関ヶ原の戦いから大坂夏の陣までの真田の歴史を、こういう主観的なしかも一方的な言葉でまとめてしまっていいものなのかどうか、私などは大いに疑問に思います。また、幸村が大坂夏の陣で最後の決戦に臨もうとする朝、江戸にいる信之は弟に語りかけます。「いよいよその日が参ったな」と。しかしよく考えれば携帯電話もない時代に、どうして大坂にいる弟の行動を同時進行で知ることができるのでしょうか。「そこは「以心電信」心を電波に乗せて伝えたのよ」などと落語的な解釈をするのが粋なのかもしれません。
軍談家や講釈師や戯作者、現代では小説家などもその仲間に入るのかもしれませんが、こういった人たちが脚色した歴史の方が実証的な歴史よりは数段面白いのも確かです。私たちは司馬遼太郎が脚色した坂本龍馬や土方歳三、池波正太郎が脚色した真田幸村や信之を以て歴史を語っているようなところがあります。
通俗の歴史をフィクションと知って娯楽として愉しむ分には罪がないわけですが、そこに「歴史にまなぶ何々」などと付くと「ちょっと待ってくれよ」ということにもなります。
最近評判の「日本維新の会」なる集団、維新八策なるものを掲げているようですが、坂本龍馬の「船中八策」と紛らわしくて警戒してしまいます。この「維新の会」の二人の親分が明治維新や昭和維新を念頭に世直しを考えているのだとしたら、面白がるだけではなく、実証的に歴史を学んで。維新なるものが何をもたらしたのか、しっかりと見極めなければいかんとも思います。

Posted by
南宜堂
at
23:21
│Comments(
0
)
歴史好き
新刊の書店に行くと来年のカレンダーや手帳のコーナーができていて、今年もわずかになったことを実感します。手帳のコーナーには歴史手帳なるものが何種類か並んでおりました。老舗の山川や吉川弘文館のものや作家の名前を冠したものまであります。歴史愛好家を自認する私ですが一度も買ったことがありません。
歴史雑誌もまた、大学の教科書のようなものから通俗的なものまで、実に様々です。一口に歴史と言っても、それを専門に研究している人からゲーム感覚で楽しんでいる人まで幅は広いようです。かつては山岡荘八や司馬遼太郎のように、企業の経営者が好んで読んでビジネスの参考にしたというようなこともあったようですが、今や歴女なる言葉に代表されるようにもっと広い層の人たちが歴史に親しんでいます。
松代藩の初代藩主であった真田信之は関ヶ原の戦いの後六十年近くの歳月を生きました。しかも死ぬ前年まで現役の藩主でした。本人は早く引退することを望んでいたようですが、幕府がそれを許さなかった。将軍がまだ幼少であるということを理由にとものの本にはありますが、それよりも幕府が真田の取り潰しを狙っていたからだろうとうがった見方もあるようです。しかし信之に後継者がなかったわけではなく、取り潰しを狙っていたという根拠は薄いような気がします。
一説には数々の戦を経験した信之の武功談を聞くのを楽しみにしていた大名や幕閣が多くて、なかなか隠居できなかったとも言われています。これはなかなか面白い見方だと思います。信之は関ヶ原の戦いには徳川秀忠の軍にいたはずですから、遅参したわけで戦いには参加していないでしょう。大坂の陣にも病気を理由に参陣していません。代わりに息子たちを派遣しています。一番の戦いといえば何と言っても徳川家康軍を追い払った第一次上田合戦ではないでしょうか。
家康を破った手柄話を江戸城でおおっぴらにできるわけではないでしょうが、平和が続いて武士たちはどうもそれに倦んでいたようにも思えます。「薄櫻記」というテレビドラマを見ていても、元禄の世では中山安兵衛の決闘の話などがもてはやされていて、この後起こる赤穂浪士の仇討ちが評判になったりするのです。
「真田三代記」があらわれるのは信之の死後のことですが、江戸時代も中期になると真田幸村の伝記が松代藩で堂々と書かれたりします。昌幸も幸村も松代藩の誇りとして語られるのです。
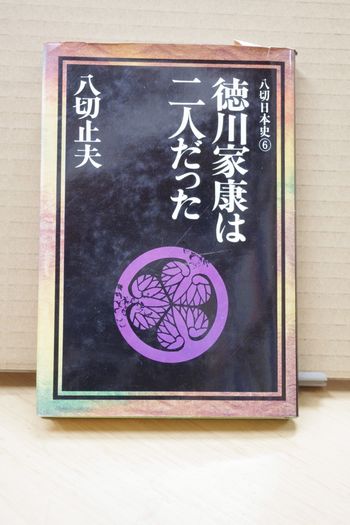
歴史雑誌もまた、大学の教科書のようなものから通俗的なものまで、実に様々です。一口に歴史と言っても、それを専門に研究している人からゲーム感覚で楽しんでいる人まで幅は広いようです。かつては山岡荘八や司馬遼太郎のように、企業の経営者が好んで読んでビジネスの参考にしたというようなこともあったようですが、今や歴女なる言葉に代表されるようにもっと広い層の人たちが歴史に親しんでいます。
松代藩の初代藩主であった真田信之は関ヶ原の戦いの後六十年近くの歳月を生きました。しかも死ぬ前年まで現役の藩主でした。本人は早く引退することを望んでいたようですが、幕府がそれを許さなかった。将軍がまだ幼少であるということを理由にとものの本にはありますが、それよりも幕府が真田の取り潰しを狙っていたからだろうとうがった見方もあるようです。しかし信之に後継者がなかったわけではなく、取り潰しを狙っていたという根拠は薄いような気がします。
一説には数々の戦を経験した信之の武功談を聞くのを楽しみにしていた大名や幕閣が多くて、なかなか隠居できなかったとも言われています。これはなかなか面白い見方だと思います。信之は関ヶ原の戦いには徳川秀忠の軍にいたはずですから、遅参したわけで戦いには参加していないでしょう。大坂の陣にも病気を理由に参陣していません。代わりに息子たちを派遣しています。一番の戦いといえば何と言っても徳川家康軍を追い払った第一次上田合戦ではないでしょうか。
家康を破った手柄話を江戸城でおおっぴらにできるわけではないでしょうが、平和が続いて武士たちはどうもそれに倦んでいたようにも思えます。「薄櫻記」というテレビドラマを見ていても、元禄の世では中山安兵衛の決闘の話などがもてはやされていて、この後起こる赤穂浪士の仇討ちが評判になったりするのです。
「真田三代記」があらわれるのは信之の死後のことですが、江戸時代も中期になると真田幸村の伝記が松代藩で堂々と書かれたりします。昌幸も幸村も松代藩の誇りとして語られるのです。
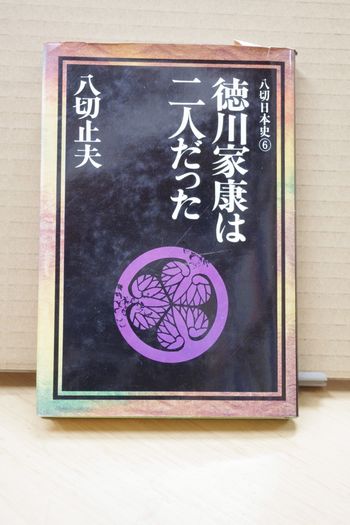
Posted by
南宜堂
at
23:33
│Comments(
0
)
辛い季節
えびす講が終わると、長野はもう冬の季節です。連休は最後のにぎわいだったようですが、光風舎は普段の日と変わりませんでした。
これから来年の3月まで、客足は減ります。何とか2回の冬を越してきたからそれなりに考えて冬ごもりをするでしょうが、商売をするものには辛い季節です。
先日小布施から来られた方が、小布施のにぎわいをうらやましがられるが、商売ができるのは半年で、あとはじっと耐えなければいけないのだと言っておられました。小布施は長野より冬が長いですから、確かにそうなのでしょう。
辛い季節といえば、いつも嘆いているように店売りにとっては今は出口のない辛い季節です。店の売上げより今日は何冊の本をネットに登録できたかが気になるというのが実情です。インターネットによって世の中ずいぶん便利になりました。しかし、反面どうもそれに縛られているなあとパソコンの画面をにらみながら思っております。

小林信彦「テレビの黄金時代」
これから来年の3月まで、客足は減ります。何とか2回の冬を越してきたからそれなりに考えて冬ごもりをするでしょうが、商売をするものには辛い季節です。
先日小布施から来られた方が、小布施のにぎわいをうらやましがられるが、商売ができるのは半年で、あとはじっと耐えなければいけないのだと言っておられました。小布施は長野より冬が長いですから、確かにそうなのでしょう。
辛い季節といえば、いつも嘆いているように店売りにとっては今は出口のない辛い季節です。店の売上げより今日は何冊の本をネットに登録できたかが気になるというのが実情です。インターネットによって世の中ずいぶん便利になりました。しかし、反面どうもそれに縛られているなあとパソコンの画面をにらみながら思っております。

小林信彦「テレビの黄金時代」
Posted by
南宜堂
at
09:50
│Comments(
0
)
咳をしても一人
昨日は一日中コタツに入っていました。ぎっくり腰になってしまい、動くと痛いのです。ずっと一人で動かずにいると自分の行く末を見るようで、不安な気分になってきます。これからますます年を取って動くのもままならなくなるとこんな毎日が続くのだろうかと。
咳をしても痛い、くしゃみをするともっと痛い。そこでこんな句が浮かびました。「咳をしても一人」もちろん私の句ではありません。尾崎放哉の句です。種田山頭火に「鴉啼いて私も一人」という句があるのだそうです。どちらの句も一人であることの侘しさ寂しさを詠んでいるのですが、山頭火の方がより自分を客観視しているような句ではないかと思います。鴉が啼いているのを、それを聞いている自分も、遠くの景色のように山頭火が見ている。それに対して放哉の句はリアルに体を丸めている彼の姿が見えてくるような印象です。
どちらが自分に近しいのかというと、それはその時になってみなければわからない。取り敢えずは、体も楽になったので店に行きます。
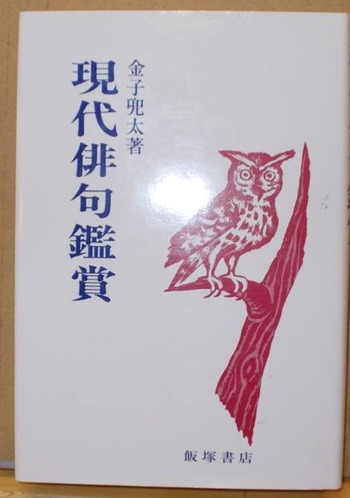
咳をしても痛い、くしゃみをするともっと痛い。そこでこんな句が浮かびました。「咳をしても一人」もちろん私の句ではありません。尾崎放哉の句です。種田山頭火に「鴉啼いて私も一人」という句があるのだそうです。どちらの句も一人であることの侘しさ寂しさを詠んでいるのですが、山頭火の方がより自分を客観視しているような句ではないかと思います。鴉が啼いているのを、それを聞いている自分も、遠くの景色のように山頭火が見ている。それに対して放哉の句はリアルに体を丸めている彼の姿が見えてくるような印象です。
どちらが自分に近しいのかというと、それはその時になってみなければわからない。取り敢えずは、体も楽になったので店に行きます。
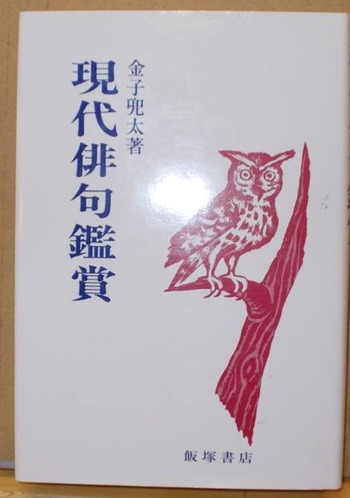
Posted by
南宜堂
at
09:11
│Comments(
0
)






